外国人スタッフ受入研修

エンジニアを中心に増加している外国人スタッフを受入れる際の心構えや日本と海外との文化の違いを理解し、スタッフが気持ち良く働ける職場環境づくりを目指します。
外国人スタッフが戸惑うであろう「常識」などの明文化、戸惑いやすい場面を想定したケーススタディを通し、どのように解決していくかを考え、事例を交えながら対応方法のコツや育成・指導ポイントを学びます。
テーマ概要
- 対象職種
- 外国人スタッフを受け入れる現場の管理職・リーダー・メンバー、採用担当者の方
- 受講定員
- 〜20名
- 研修日数
- 1日(6時間)
カリキュラム一例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
|
1.オリエンテーション
2.異文化とは何か
3.外国人スタッフとのコミュニケーション
4.ともに働くうえでのビジネスマナーの基本を共有する
5.外国人スタッフと、ともに“協働”していくために |
(1)外国人スタッフと協働することについて考えてみる (2)現在直面している悩みなどを共有する ・外国人スタッフがお客様のお子様に勝手にお菓子をあげてしまう
(1)文化の違いを知る (2)当たり前が違うということ (3)立場を変えて考える ・日本でよくある 「暗黙の了解」「常識」は通じない?
(1)簡単な日本語を使う (2)外国人スタッフが持ちがちな不安・悩みを知ろう (3)受け入れ態勢を準備しておく ・成果に対しての意識の違い、日本人は細かすぎる?
(1)日本の仕事のやり方と海外の違い (2)これだけは守ってほしいことの共有 ・お客様は神様!?なんて理解できない
(1)受け入れの際の役割は (2)時間の感覚・評価基準 (3)ルールを作る (4)共通言語を創る ・外国人スタッフが遅刻を繰り返すがカイゼンせず悩んでいる |
| 項目 | |
|---|---|
| 内容 |
| 項目 |
1.オリエンテーション
2.異文化とは何か
3.外国人スタッフとのコミュニケーション
4.ともに働くうえでのビジネスマナーの基本を共有する
5.外国人スタッフと、ともに“協働”していくために |
|---|---|
| 内容 | (1)外国人スタッフと協働することについて考えてみる (2)現在直面している悩みなどを共有する ・外国人スタッフがお客様のお子様に勝手にお菓子をあげてしまう
(1)文化の違いを知る (2)当たり前が違うということ (3)立場を変えて考える ・日本でよくある 「暗黙の了解」「常識」は通じない?
(1)簡単な日本語を使う (2)外国人スタッフが持ちがちな不安・悩みを知ろう (3)受け入れ態勢を準備しておく ・成果に対しての意識の違い、日本人は細かすぎる?
(1)日本の仕事のやり方と海外の違い (2)これだけは守ってほしいことの共有 ・お客様は神様!?なんて理解できない
(1)受け入れの際の役割は (2)時間の感覚・評価基準 (3)ルールを作る (4)共通言語を創る ・外国人スタッフが遅刻を繰り返すがカイゼンせず悩んでいる |
こんな人におすすめ
- 外国人スタッフを受け入れる現場の管理職・リーダー・メンバー
- 採用担当者の方
研修を受講するメリット
-
外国人スタッフと、受入側の日本人スタッフの双方が気持ち良く働ける職場環境をつくるために、「違い」を理解する
本研修では、まず外国人スタッフと協働することについて考えます。また、既に外国人スタッフを受け入れている場合には現在直面している悩みなどを共有します。
考え方や行動・・・「当たり前」の違いは、育った環境や文化から発生します。その違いを理解し、受け入れるために、日本で働く方の多い主な国の文化を学びます。 -
外国人スタッフと、ともに“協働”し、気持ち良く、戦力として活躍してもらうためのコツを学ぶ
立場が変われば、受入側のスタッフも「外国人スタッフ」であり、異文化、となり得ます。自身に置き換えて考えてみる時間を設けることで、気持ちに寄り添い、考えるキッカケをつくります。また、働くうえで守ってほしいことを理解してもらうための関わり方や、日頃の業務の伝え方を学びます。



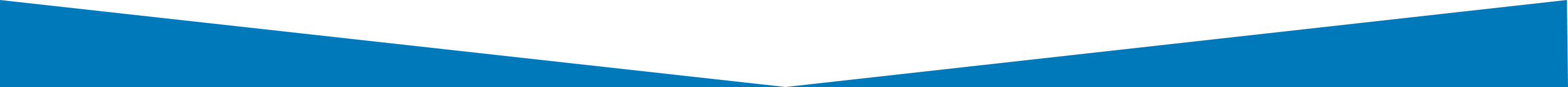

受講者の声
各国の文化や人柄や性格、それに合わせた良好なコミュニケーションの取り方など参考になりました。
外国人スタッフのあるあるや講師の実体験に基づいた話が非常に分かり易かったです。具体例がとても参考になりました。
今までは、入社していただいた外国人スタッフ自身のスキル任せだったので、研修で得た気づきをもとに、受入体制を強化していきたい。